「ショスタコーヴィチとスターリン」は「ショスタコーヴィチの証言」の作者ヴォルコフが『証言』は偽書だという批判に答えて書いた著書です。証言では省略されたショスタコーヴィチとスターリンの対決の様々なシーンを当時の資料から読み解いたものです。
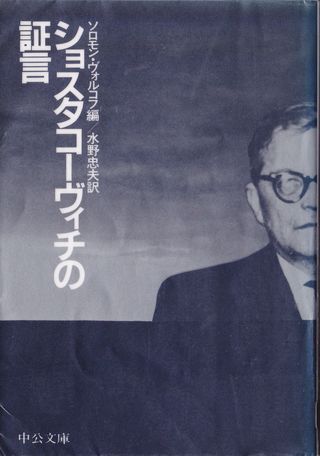
『証言』に関しては、ヴォルコフの信憑性の弁護に使った小細工の嘘が暴かれ、『証言』そのものの内容に関しても疑問符を付けるむきが多いようですが、とんでもない勘違いだと思います。
確かにショスタコーヴィチのサインの扱いについての不適切な処理は問題ですが、『証言』の内容については彼の音楽を聴いて判断すべきです。現に西欧の大部分の演奏家は『証言』の内容を支持している。これは演奏することにより彼の音楽を良く理解した結果の判断だと思います。
「ショスタコーヴィチとスターリン」では、スターリンを登場させて、当時の資料(公式資料、関係者がやりとりした手紙やメモ)はふんだんに使い、ヴォルコフは彼の主張をより顕かに提示しています。
『証言』が公開されたのが1979年、「ショスタコーヴィチとスターリン」は2004年。25年後に書かれた反論の書となります。

ヴォルコフは、「ショスタコーヴィチとスターリン」のプロローグで、ロシアでは皇帝の権力に異議申し立てをする人物像として「僭称者」、「聖愚者」、「年代記作者」の三種類があること提示します。
「僭称者」は皇帝の名をかたることにより時の皇帝に正面から対抗する人物、「聖愚者」とは聖なる愚か者として狂っているふりして皇帝への批判の声を裏から発する人物。「年代記作者」とは皇帝の評価を歴史の審判として行う人物となります。
スターリンは二代目のソビエト連邦の皇帝であったわけで、反対意見の持ち主を粛清の嵐で黙らせてきた。そのため、全ての芸術家は、彼の時代を生き延び、自己主張するにはこの三つの仮面を適切に選び、操りながら生きていく必要がありました。
いくつか中心となる部分を引用してみましょう。
ショスタコーヴィチとスターリンの対決シーンの中でポイントとなるのは、①1936年 上演中のマクベス夫人に関するプラウダでの批判的論説と、②1948年 党による作曲家たちへの批判決議とを巡る二人のやりとりです。これが面白い。
①「音楽ならざる荒唐無稽」というプラウダの批判記事について、第2章からです。
スターリンは、ソ連では、広く大衆に受け人れられ、習得される「全人民的」な文化が創造され、宣伝されねばならないという、確固たる信念をもっていた。そのような全体的な「文化的識字力」が、国を進歩的な国家に変容させることを促進するはずだった。スターリンは、政治的な養育と管理の手段としての文化の重要性を非常によく理解していた。だが、その際、彼の個人的な芸術的趣味はもっぱら実利的なものとはいえなかった。
スターリンは、多くの二十世紀の政治的な指導者と異なって、文化の狂信者と呼ぶことができた。彼自身の計算によれば、彼は一日に平均五百ページを速読していた。もちろん、それは基本的にあらゆる類の実務的な書類だった。だがスターリンは、多くのーーノンフィクションやフィクションのーー文学作品も読んでいた。これらすべては、注意深く、鉛筆を片手に、関心を示す印やコメントが余白に書きとめられていた。
古典的な音楽に対するスターリンの関心は、正真正銘のものだった。彼は古典的な音楽にしばしば耳を傾け、明らかに楽しみとしていた。それは第一に、ロシアのオペラとバレエーーチャイコフスキーグリンカ、ポロディン、リムスキーいコルサコフ・・少し劣るがムソルグスキーであった。だが、スターリンのお気に入りには、ビゼーやヴェルデイも含まれていた。
つまり、彼は暴虐なことはしたが、全て意図してやったことで、狂っていたわけではなかった。芸術を解する教養ゆたかな人物であったが、政治的には共産党の信念に基づき判断し、自己の芸術的好みで判断基準が揺らぐことはなかった。ということです。

一九三六年の記憶に残る一月の晩、スターリンが「マクベス夫人」の上演を訪れたとき、指導者の脳裏には、個人的な嗜好を司令的に普及させること以上に、もっと重要な判断があった。スターリンは、自分の感情を、そのときの戦略的な要請に従属させる能力を誇りにしていた。そしてこのとき、新たな国家の「ソ連的モラル」を積極的に主張することが求められていた。政府は、まもなく受理される、堕胎禁止の法律と家族と結婚についての新たな法典を計画していた。というのも、スターリンの考えでは、ソ連の家族は、あらゆる手段を尽くして強化されなければならなかったからである。指導者のイニシアティヴにより、離婚は著しく困難になった。スターリンが子どもたちを両手に抱いた写真が定期的に出版物に現われるようになった。そしてここで突然、「自由恋愛」(あるいは、「音楽ならざる荒唐無稽」におけるスターリンの言葉で言えば、「商人の妻の好色性」)を賛美するオペラが出現し、そこでは嫌いな夫との離婚の問題が、殺人の手段によって、簡単に残忍に解されていたのである。
これが、「音楽ならざる荒唐無稽」と題されるショスタコーヴィチへの批判記事がプラウダに掲載されたという事件の理由だというわけです。
なるほど、スターリンは暴虐な男だったけど、女に関しては真面目だったのね。日本の某業界とは大きく異なるということのようです。
説得力のある謎解きですね。
この後、次のような記述が続きます。
いま私たちに完全に明らかなのは、「形式キ義」や「インテリの」芸術との戦いのキャンペーンは、スターリンによってあらかじめ着想されていて、一定の計画に基づいて実現されたということである。これについて、「プラウダ』紙上に次のような「反形式主義」の論説が素早く次々に現われたことが証明している。映画への批判(三月十三日付「歴史的真実の代わりの粗野な図式」)、建築(三月二十日付「建築のカコフォニー」)、絵画(三月一日付「へぼ絵描きたちについて」)、演劇(三月九日付「うわべの輝きと偽善的内容」)がそれである。ここでのすべては、スターリンが演出した文化政策の攻勢の論理によって、理解され、説明されるのである。
この辺りは当時の資料で完全に証明されているということなのでしょう。素晴らしい説得力だと思います。
しかし、なんと言うか、酷い粗野なタイトルばかりだね。貧困な精神だったのはプラウダの批判記事の作者たちでしょうね。
そして、この批判に対するショスタコーヴィチの反応の分析が第3章に続きます。この内容がまた凄いです。

ショスタコーヴィチは、表面的には生活には不向きで、日常的な状況に対してはナイーヴに見受けられたが、どんな傑出した文化活動家でも、その創作の運命や生命さえもスターリンが取る個人的な態度に依存してしまうような生涯の決定的な瞬間において、彼は、新たな状況にたいして驚くべき理解を示した。
具体的なイデオロギー的指示は、目もくらむような速さで、しばしば予測不可能な神秘的な方向へと変わった。その進化について予言することは困難であり、自尊心や創作上の誠実さを失わずにそうした指示に従うことは不可能だった。またそれは高く評価されるようなものでもなかった。
生きながらえる唯一のチャンスは、ソ連史のあらゆる新たな紆余曲折に際してスタ1リンが示す文化的言説の、書かれることのない変数を理解することにあった。これらの変数はしばしば両義的であり、それ自体、スターリンの構想の一部をなしていた。
(中略)
こうした新たな規則の認識は、彼がアル(ンゲリスクで「音薬ならざる荒唐無稽」を読んだ、その運命的な日にショスタコーヴィチに訪れた顕現であった。まさにそれゆえに、ショスタコーヴィチが、アルハンゲリスクから戻ってきたときに会いに来た友人たちに述べた最初の言のなかに、「ご心配なく。彼らは私を必要としています」という重要な言葉があったのだ。これは冷静なものであり、ショスタコーヴィチのような、若く傷つきやすい人にとっては、根本的に新しい状況評価であった。人生においても創作においても、生きながらえるためにはまったく新たな綱領が必要だったのである。
なるほどね。だから彼は第4番の交響曲の発表を見合せ、第5番の交響曲に勝負をかけたというわけです。
ショスタコーヴィチはボルシェヴェキに共感する家族の中で育ち、初期段階では共産党による革命に共感していた。彼は、プロコフィエフのように革命直後のソ連から亡命することは、まったく考えていなかった。実際、ショスタコーヴィチの第2番、第3番の交響曲は共産党の革命に対する讃歌として書かれています。
『後年、ショスタコーヴィチは、自分の十五の交響曲のうち、「二つは、おそらく、満足できる出来ではない。それは交響曲第二番と第三番だ」と認めていた。彼は、自分の第四番を正当にも決定的な飛躍として評価していた。』
ということだと思います。共産党の言うことを聞いた初期の交響曲は駄作だったということです。
次に
②1948年 党による作曲家たちへの批判決議

この写真はわざと傾いているのですかね(^^;;;
「ショスタコーヴィチとスターリン」の第6章から
1965年に「反ソヴィエト的」執筆活動によって矯正収容所に送られたアンドレイ・シニャフスキーの回想によると、ある囚人が茨ましそうに彼にこう言ったという。「あんたたち作家さんにとっては、死ぬのも役に立つんだよな」。つまり、作家はネガティヴな経験でさえも利用して芸術作品に変えることができる、というのである。
それはまさにショスタコーヴィチがしたことだった。頭のてつべんから爪先まで官製の汚物にまみれながら、彼はそれを黄金のような音楽ーーヴァイオリン協奏曲第一番と「反形式主義的ラヨーク」ーーに変えることができた。しかもこの二作品はまったくタイプが異なる。一つは悲劇の一大絵巻、もう一スコをローフ方は旅芸人の見世物である。だがどちらも力のこもった、全身全霊を棒げて書かれた作品である。それ以外にもう一つの典型的なショスタコーヴィチの特徴が両作品を結びつけている。どちらの作品も「机のなかへ人れるために」、つまり、すぐに演奏してもらえるという希望がないままにつくられたにもかかわらず、ショスタコーヴィチは未来の聴衆のために、彼らにとって興味深く聴くことができるおもしろい作品になるように気を配っていた
ショスタコーヴィチのもっ稀有の特質ーーつねに聴き手の受け止め方に注意を払い、聴衆が作品の最後まで関心を保ちつづけられることを目指すーーは、しばしばスノッブな批評家を苛立たせ、途方に暮れさせるショスタコーヴィチの交響曲第五番のフィナーレは悲劇的なのに、なぜか聴衆が演奏後に歓喜のあまり熱狂するのが彼らには不満だった。だがそれは、「反形式主義的ラヨーク」のフィナーレのスコモコーフカンカンが刺激的であるのと同じ理由なのだ。つまり、真の旅芸人にして聖愚者たるショスタコーヴィチは、創作行為の火花のなかで自己表現することによって悪の力を克服しようとしているのである。悲劇的な音楽というのは、必ずしも単調で退屈でなければならないわけではない。同様に諷刺も、単に辛辣で教訓的であるだけではなく、おもしろいものにもなりうるのだ。
この記述が「ショスタコーヴィチとスターリン」全体の眼目であると思います。「耳なしも同然」のスノッブな批評家には、『創作行為の火花』を理解することは出来ない。『聖愚者たるショスタコーヴィチの風刺』も届かないということです。
そして同じ章の少し先に記述されているように
よく知られているように、スターリンはこの手のものに大きな注意を払っていた。いまでは公表されている準備段階の秘密メモによると、「形式主義者たちーのリストは最後の最後まで揺れ動いていた。リストの先頭はプロコーフィエフになったりミャスコフスキーになったりした。また、リストに載る顔ぶれも変わりつづけた。最終版でショスタコーヴィチがリストの先頭に粥えられたのは、明らかにスターリンの意向を反映している。決議に記されているように、ショスタコーヴィチは「音楽の発展を行き詰まらせ、音楽芸術を減ぼすような、ソ連の音楽文化には無縁であるはずの傾向をソ連音楽文化関係者たちのあいだに広めたこと」に対して重大な責任があるとスターリンは考えていたのである。
近年明らかになったのであるが、こうしたことすべてについてアメリカ人の言い方を借りるなら「馬の口から(「確かな筋から」という意味)」知ったらしい。スターリンの秘書アレクサンドル・ポスクリヨーブィシェフからの電話を受け、クレムリンに呼び出された。スターリンは、ポスクリヨーブィシェフがみでからショスタコーヴィチに党決議の文面を読み聞かせるように指示したのだった。
スターリンのこの行動は、いつものやり口と同じく、二重の意味をはらむ狡猾なものだった。一方でそれは、指導者か個人的に注目しているのだという合図であり、その一方で「打ち叩きつつ、泣くことを許さない」というサディストの鞭を思わせる。それと同時にスターリンはおそらく、ショスタコーヴィチがこの「鞭」をどのように受け止めたのかをポスクリヨープイシェフから聞こうと思ったのだろ。
神示質で敏感なショスクコーヴィチは、もらろんこうしたことを全て大きな困惑と感じた。のちに彼は回想しているのだがポスクリョが決議の文面を読み上げているあいだ、作曲家は彼の顔を見ることができず、その代わりにこのスターリンの書が履いていた黄色い革のプーツの先端を凝視していたのだという。決議が掲載されるとすぐに「公的処分」が始まった。ショスタコーヴィチはモスクワとレニングラード音楽院から解雇された。彼の作品の多くは.(他の「形式主義者たち」の曲と同様)レパートリから外された。スターリンは一九一三年以来、実に十六年間棚上げされていた作曲家同盟の設立を推し進めることにした。
そして、『証言』のこの有名な記述
処刑を待ち受けることは、わたしを一生苦しめつづけた主題のひとつである。わたしの音楽にはこの主題にあてられたページがたくさんある。ときどき、このことを演奏者に説明したいと思ったりしたのは、そうすれば、演奏者が作品の意味をよりよく理解できるのではないかと考えたからだ。しかしあとで、それは控えておいたほうがよいと思い直した。だって、よくない演奏家にはいくら説明してもどうせわからないし、才能ある人間なら、自分で感じるはずではないか。それでも、最近言葉のほうが、音楽よりももっとよく人間に理解されるものだと確信するようになった。残念ながらそうなのだ。音楽に言葉を結びつけると、音楽は誤解されにくくなる。
あるとき、わたしの音楽の最大の解釈者を自負していた指揮者ムラヴィンスキイがわたしの音楽をまるで理解していないのを知って愕然とした。交響曲第五番と第七番でわたしが歓喜の終楽章を書きたいと望んでいたなどと、およそわたしの思ってもみなかったことを言っているのだ。
この男には、わたしが歓喜の終楽章など夢に考えたことがないのもわからないのだ。いったい、あそこにどんな歓喜があるというのか。第五交響曲で扱われている主題は誰にも明白である、とわたしは思う。あれは《ポリス・ゴドノフ》の場面と同様、強制された歓喜なのだ。それは、打たれ、「さあ、喜べ、喜べ、それがおまえたちの仕事だ」と命令されるのと同じだ。そして、段打たれた者は立ちあがり、ふらっく足で行進をはじめ、「さあ、喜ぶそ、喜ぶぞ、それがおれたちの仕事だ」という。
これがいったいどんな礼讃だというのか。それが聞きとれないなんて、耳なしも同然だ。ところが、ソ連作家同盟の指導者で、スターリン批判後に自殺した作家アレクサンドル・ファジェーエフ(1901~56)にはそれが聞こえた。それで彼は、まったく自分だけの個人的な日記に、第五番の終楽章は果てしない悲劇だ、と書きこんだのだ。きっと、ロシアのアルコール中毒患者に固有な魂で感じとったに相違ない。
第五交響曲の初演を聞ぎにきた人々は、もっとも快い気分で泣いていた。だが、第七交響曲の勝利の終楽章について語るのは、まったくもって愚かしい。それには根拠がさらに少ないのだが、このような解釈が現われている。
この記述はムラヴィンスキーの解釈を正しいと考える多くの人々に衝撃を与え、激しく反発された部分です。しかし「ショスタコーヴィチとスターリン」の上記のいくつか引用を踏まえると、本人の言葉として極めて自然に感じます。従って、西欧の演奏家はヴォルコフの『証言』を信用するのです。
引用するために改めて読み直しましたが、この『証言』の文章は素晴らしいですね。日本語訳が良くできているということもあると思います。ここまで引用してきた「ショスタコーヴィチとスターリン」の直訳調の翻訳文体とはまったく異なります。
さらにスターリン直接の電話もあったらしい。次の章になりますが、
三月十六日、ショスタコーヴィチのところに電話があり、これから同志スターリンがあなたと話をされるので受話器から離れないように、という予告を受けた。最初、自分はからかわれているのだと作曲家は思った。だがその後、こんな危険な冗談を言う者などいるはずがない、と考え直した。そして実際、受話器からは聞き覚えのあるスターリンの声(1943年にポリショイ劇場で新しい国歌について議論されたときに、彼はスターリンと会ったことがある)が聞こえてきた。スターリンは、どうしてあのような重要な任務を断ったのか、とショスタコーヴィチに尋ねた。
ショスタコーヴィチは頭の回転が速く、指導者と対話するときにも怖けづいたりしないということをすでに一度証明していたが、今回もまた動揺することなく(どうやらあらかじめ心の準備ができていたようである)、自分がアメリカへ行かないのは、もう一年以上も自分や仲間たちの音楽がソ連で演奏を禁止されているからだ、と答えた。
すると前代未聞のことが起きた。作曲家を追い詰めようとしたスターリンのほうが動揺したのである。みずからのイデオロギー的指令が実行されているかどうかを細部まできっちり監督し、すべてを把握していることを誇り、そしてそれを事あるごとに誇示し、強調してきた指導者は、今回はその事態を知らなかったような様子をして、ひどく驚愕してみせた。「演奏されないとはどういうことですか? どうして演奏されないのですか? 一体どういう理由で演奏されないのですか? 」ショスタコーヴィチは、レパートリーリー委員会(つまり検閲)がそのような命令を出していることを説明した。するとスターリンは、自分のほうから譲歩してきた。「いや、われわれはそのような命令は出していません。レバートリー委員会の者たちに訂正しておかなければ」。そして彼は話題を変えた。「で、体の調子はどうなんですか?」
この部分は『証言』では、次のように叙述されています。
いや、行きません、とわたしは答えた。わたしは病気で、飛行機には乗れない、飛行機に乗ると、すぐに酔ってしまう、と言った。当時の外務大臣モトロフが説得しにきたが、それでもやはり、わたしは拒否した。
そのとき、スターリンから電話がかかってきた。「指導者にして教師」は例の押しつけがまいやり方で、どうしてアメリカに行きたくないのか、とたずねはじめた。行くことができないのです、とわたしは彼に答えた。いま、わたしの友人たちの音楽も、わたしの音楽も演奏されなくなっています。アメリカでそのことをたずねられたら、わたしはどのように答えればよいのでしょうか。
スターリンは驚いたようなふりをした。「演奏されなくなっている? どうして演奏されないのです? いったいどのような理由で演奏されないのです? 」
レパートリー委員会の命令があり、プラック・リストがあるのです、とわたしはスターリンに答えた。「そのような命令を出したのは誰です? 」とスターリンがたずねた。わたしは当然、「たぶん、指導部にいる同志の誰かでしよう」と答えた。
ここで、きわめて面白いことがはじまった。「いや、われわれはそのような命令を与えはしなかった」とスターリンは言いきった。彼は「われわれ」というように自分のことを呼んでいた。「われわれ」と自分のことを呼んでいたのは、皇帝ニコライ二世であった。そして、この件に関してはレパートリー委員会が努力しすぎている、正しくない創意性を発揮している、と同じことをくり返していた。われわれはそのような命令を出した覚えがない、レパートリー委員会の同志の誤りを訂正しなければならない、などと言っていた。
二つの本の記述は完全に一致しています。ということは何らかの裏付けとなる資料があるのでしょう。
そういう資料があるということは「ショスタコーヴィチは共産党のプロパガンダに忠実な作曲家だった。彼の5番、7番の交響曲の終楽章は歓喜の行進であるという解釈のバカバカしさを証明してくれるでしょう。
「ショスタコーヴィチとスターリン」は6000円近くする本で慶応義塾大学出版会から発刊されています。学術書ということなのでしょう。だからかもしれませんが、直訳調の文体でとても読みにくい。
「ショスタコーヴィチの証言」は中央公論で発表され、同社から出版され、更に文庫にもなっています(冒頭部分の写真は文庫版です)。従って、日本語としてこなれた読みやい本になっています。この差は大きい。
多分、大部分のショスタコーヴィチ好きは『証言』を読み、その後の反論記事を読み、証言の内容に疑問をもっているのではないだろうか。
4人の共訳ですが、あとがきを書いている亀山さんが後記で
「証言」の真をめぐる対立は、西間と東側の対立といった光景を呈してきた点も特筆すべきことであると思う。たとえば、当初は、「証言」に反発を見せた息子のマクシムも、西欧に亡命した後は、ヴォルコフに対して好意的な度をとり、本書のロシア語版の再版(2006)の際には(翻訳では割愛したが)姉のガリーナとともに序文を寄せている。
本書に推薦文を寄せているのも演奏家が多く、ヴァイオリニストのウラジミール・スビヴァコフは本書のロシア語版にエッセイを寄稿している(同しく本書では割愛した)。また、「証言」を支持する人々のなかには、少なからず文学者が含まれていた。優れた文学史家で「プーシキン館」の著者であるアンドレイ・ビートフ、近年物故した「雪どけ時代」の詩人で、交響曲第13番「パービー・ヤール」の詩を書いたエヴゲニー・エフトゥシェンコらである。
今日、「証言」に対してとるべき態度は、一つである。「証言」それ自体の真贋についてほぼ決着はつき、その信憑性は疑われるが、書かれている内容については、西側では知られていない事実が多々含まれ、また随所に優れた文学的洞察が垣間見られるとして限定的ではあるが、一定の評価を与える立場である。ショスタコーヴィチ再評価の歴史において「証言」が果たしたパイオニア的な役割はけっして無視することはできないだろう。
こういうのを研究者の典型的な客観的記述というのでしょうね。間違ったことは何も言っていないが、明快な自己主張をさける。『「証言」が果たしたパイオニア的な役割』を評価しておきながら、その内容を積極的に肯定しない。立派な態度だとは思うが、共感はできません。「だから、こういうヘナチョコな翻訳でよし」としたのだろうと言いたくなるね。
残念なことです。
